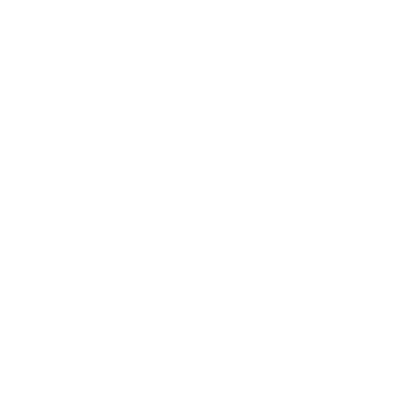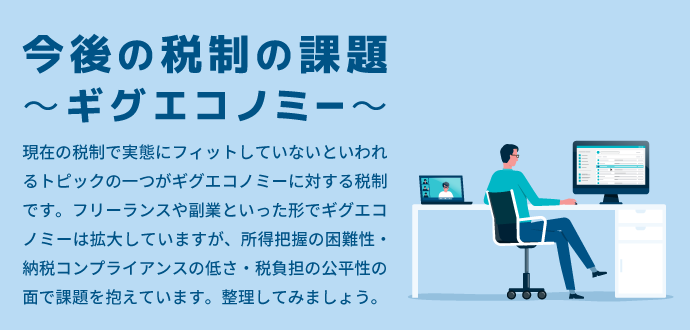
1.はじめに
令和7年度税制改正大綱において、所得税に関するいわゆる「103万円の壁」の改正が行われました。それにより給与所得控除の金額が引き上げられましたが、同時に社会保険料の支払が増加する可能性があるため、手取り額が必ずしも増えるとは限りません。
税制改正は、所得の再分配や課税の公平性が担保するために、時代の変化に合わせて行われますが、昨今の働き方の急激な多様化に対し、税制のあり方が現状にフィットしていないという見方もあります。
そこで今回は働き方の変化”ギグエコノミー”と現在の所得税制の課題について解説します。
2.現在の所得税制度のメリット・デメリット
今回はギグエコノミーに最も影響が大きい所得税について解説していきます。その前に、基本的知識として現在の日本の税制における所得税のメリット・デメリットをみてみましょう。
| 徴収方法 | 所得に対して課税される。会社員は天引きの形で徴収され、個人事業主の場合は売上先が源泉徴収する又は確定申告時に納付する。 |
|---|---|
| 長所 | 累進課税制度をとっているため、高所得者の税負担が重くなり公平性が高い。 |
| 短所 | 所得が上がるほど税負担が増えるため、労働意欲を減退させやすい。 |
このようにメリットデメリットがあり、世相に合わせて税制は適切に改変していく必要があります。
3.ギグエコノミーに対する税制のミスマッチ
前項でも触れたように、税制は労働人口の変動や景気の変化に合わせて改正していく必要がありますが、時代の変化に税制が追いついていない部分もあります。現在の税制で実態にフィットしていないといわれるトピックの一つがギグエコノミーに対する税制です。ギグエコノミーとは、インターネットを通じて単発や短期の仕事を個人が請け負う働き方、またはその経済活動を指し、この働き方をする人のことをギグワーカーといいます。具体的には、Uber Eatsの配達員やクラウドソーシングサイトでの仕事などが該当します。ギグエコノミーの特徴は、企業に雇用されず、時間や場所にとらわれず自分のスキルや経験を活かして働けることです。フリーランスや副業などといった形でギグエコノミーは拡大していますが、税制や社会保障制度とのミスマッチが発生しているといわれています。次項で具体的にみていきたいと思います。
4.ギグエコノミーに関する税制の課題
ギグエコノミーにかかる所得税については以下のような問題点があるといわれています。
①所得把握の困難性
ギグワーカーは多様なプラットフォームを利用して収入を得ているため、税務署がその分散した所得を漏れなく把握するのは困難であるといわれています。証跡が残らない現金取引や証跡を追いにくい海外取引になると所得の網羅的な把握は更に難しくなります。
②納税コンプライアンスの低さ
会社員であれば納税を意識しなくても所得税も消費税も社会保険料も基本的に自動で納付されますが、ギグワーカーの場合は所得税と社会保険料を自ら納税をする必要があります。そのため、①にも通じることですが、納税漏れが発生しやすくなります。さらに、税務知識が不足していると、確定申告を誤る可能性も高いといえます。
③税負担の公平性
現在の税制では、会社員の給与所得には個別の経費計上は認められませんが、給与収入に応じて一律に控除される”概算控除”が適用されます。ギグワーカーの事業所得は、実際にかかった経費を計上する”実費控除”となります。また、厳密には税金ではありませんが、手取金額に大きな影響を及ぼす社会保険料についても、会社員の場合は会社と半分ずつの負担になりますが、ギグワーカーの場合は全額自己負担となります。このような点から現在の税制は公平性が担保されていないのではないかという議論があります。
5.おわりに
前項のような課題を解決するため、今後はより簡単に申告ができる制度が構築されるといわれています。その構築にはマイナポータルの普及が前提になると考えられますので、今すぐの実現は難しいかもしれませんが、将来的には給与所得者と事業所得者の壁がなくなり、申告手続が簡単になることで申告漏れも減少していくと考えられます。