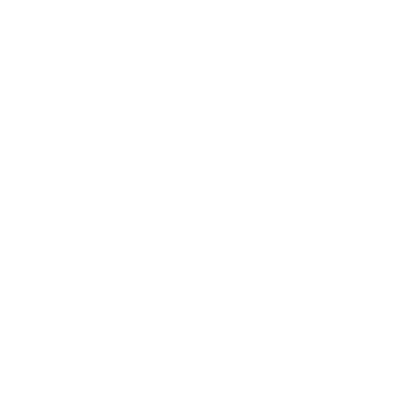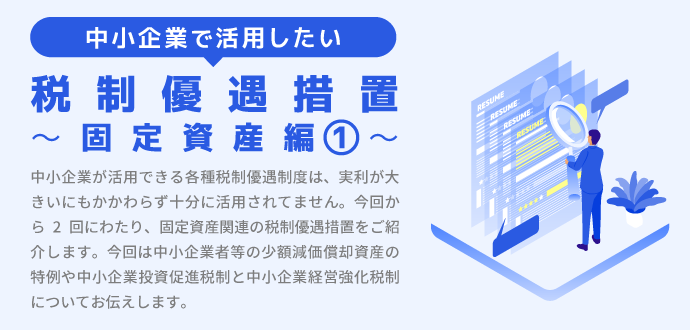
1.はじめに
先般の参議院選挙では、消費税および社会保険料の引き下げが重要な政策論点として浮上しました。これらの政策は、消費者の負担軽減にとどまらず、消費税の低減による企業の設備投資促進や、社会保険料の削減による企業負担の軽減を通じて、最終的には給与の引上げにつながるという主張がありました。中小企業にとっては、税制のわずかな変更でも事業運営に大きな影響を及ぼすため、こうした動向には引き続き注目が必要です。ただし、市場動向や政治情勢により今後の税制設計は予断を許しません。一方で、現時点においても中小企業が活用できる各種税制優遇制度は整備されています。特に、固定資産や設備投資に関連する税制優遇措置には、実利が大きいにもかかわらず十分に活用されていないものも見受けられます。今回から2回にわたり、中小企業が現行の税制枠内で活用可能な固定資産関連の税制優遇措置をご紹介します。
2.中小企業者等の少額減価償却資産の特例
この特例はこれまで何度も税制改正によって延長されており、令和6年度の改正により令和8年3月31日まで延長されている状態です。内容は、中小企業者等が取得価額が30万円未満である減価償却資産について、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというもので、限度額は300万円とされています。
限度額が「30万円未満」とされていますが、取得価額が10万円未満の資産は消耗品と同じ扱いで取得年度に全額損金算入できるため、実質的には10万円以上30万円未満の資産の合計額が対象となります。例えば、26万円の資産を12個、合計312万円を購入した場合、11個分の286万円まで適用を受けられます。限度額まで償却不足額はありますが、残りはこの適用を受けられないことになります。また、30万円未満の判定は、会社の会計処理が税込・税抜処理であるかで変わってきます。例えば、免税業者であれば税込経理しか選択できないため、税込価格で30万円未満か否かで判定します。
また、所有権移転外リース取引に係るリース資産についても、この特例は適用できるため改めて検討されることをお勧めします。
3.中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制は名称や内容が似ているため混同されやすいものの、様々な点で異なります。両者の違い等詳細は次回で解説しますが、簡単に比較すると以下のようになります。
| 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 | |
|---|---|---|
| 節税メリット | 以下から選択 ①特別償却:取得資産の30%を費用として即時計上可能 ②税額控除:取得価格の7%(資本金3,000万円以下の中小企業が対象)を法人税から控除可能 |
以下から選択 ①即時償却:取得費用をその年度に全額経費として計上可能 ②税額控除:取得価格の10%(資本金3,000万円未満)または7%(資本金3,000万円超1億円以下)を法人税から控除可能 |
| 対象資産 | 比較的限定される | 対象資産は広い |
| 運用手続 | 確定申告時の申告のみ | 「経営力向上計画」の事前認定が必要。A~D類型に応じて、工業会等の証明 |
中小企業経営強化税制の方が取得年度における節税効果は大きいものの、追加の手続が必要となります。税額控除ではなく減価償却でメリットを享受しようとした場合、両者は特別償却と即時償却という点で異なりますが、いずれも償却不足額を翌期以降に繰り越せるという点は共通しています。詳細は次回に譲りますが、取得年度に償却限度額まで減価償却費を計上せず、翌事業年度に残りの枠を用いて計上することが可能になるため、非常に使い勝手が良いといえます。
4.中古資産の耐用年数
近年では中古で固定資産を購入するケースが増えているようです。中古資産を購入した場合も、新品の資産と同様に国税庁が公表している耐用年数表に従って法定耐用年数を採用しているケースも多く見られます。ただし、一口に中古資産といっても品質や古さにはばらつきがあるため、税法でも法定耐用年数ではなくその事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数を採用することも認められています。本来的には、個々の資産の状況に合わせて耐用年数を決定できるのが望ましいですが、一般的にそれは困難です。そこで、簡便法により算定した耐用年数を適用できる仕組みが設けられています。
簡便法による耐用年数は以下のように算定します。
残存耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
② 法定耐用年数の一部を経過している資産
残存耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%
①のケースでは減価償却率が大きく異なるため、中古資産を購入した際は必ずご検討されることをお勧めします。
ただし、「その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(同一の新品資産を取得する場合の取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用する」とされています。つまり、再取得価格の50%を超える資産はコンディションが良く、新品に近い状態で使用できることが予想されるため、法定耐用年数を適用しなければなりません。
5.おわりに
今回は中小企業にのみ適用できる固定資産まわりの税制優遇措置の一部をご紹介しました。実際に適用する場合は、対象法人等細かな規定がありますので事前によくご確認ください。
次回は、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制について細かいポイントを解説したいと思います。